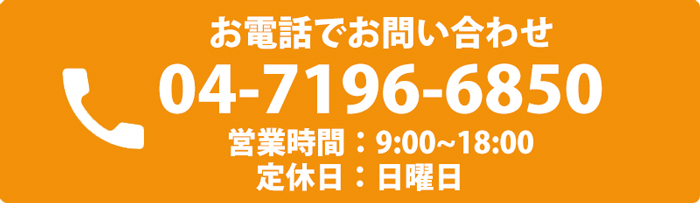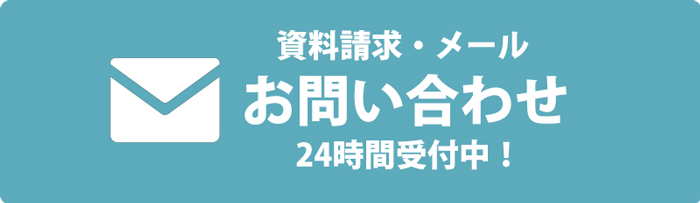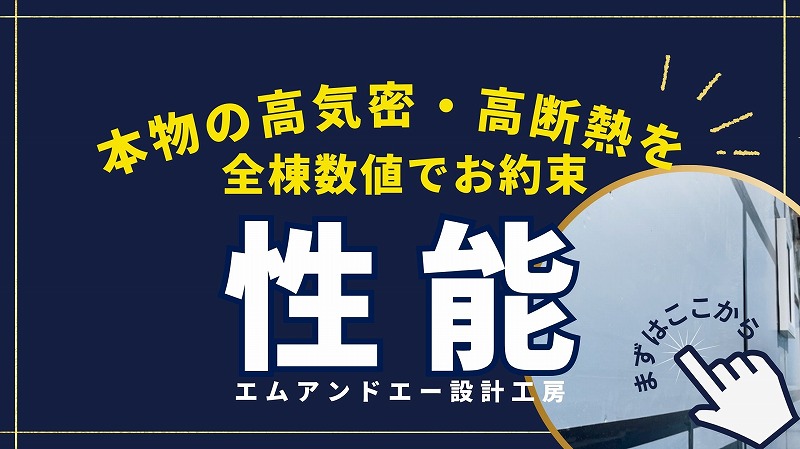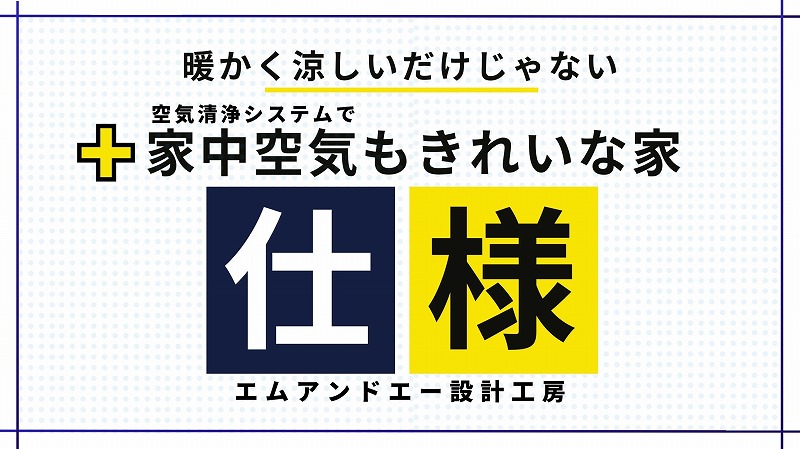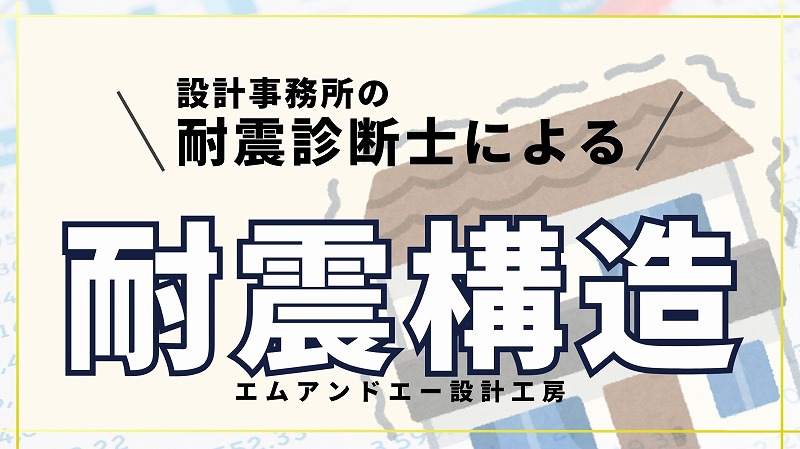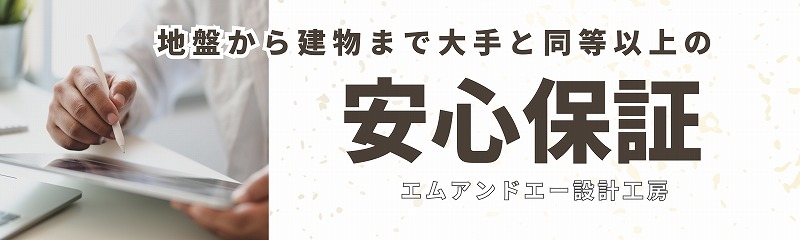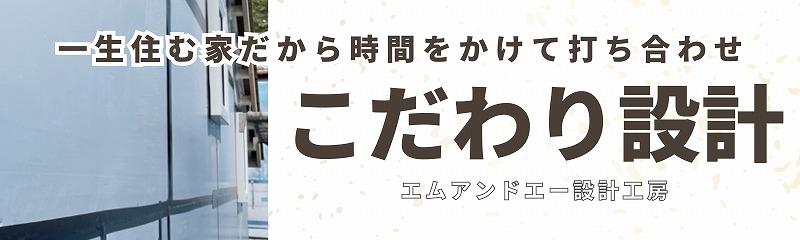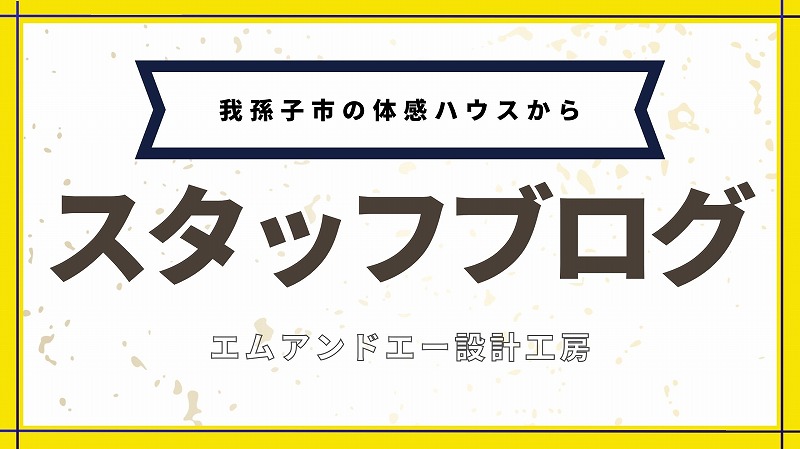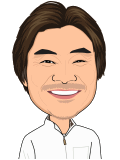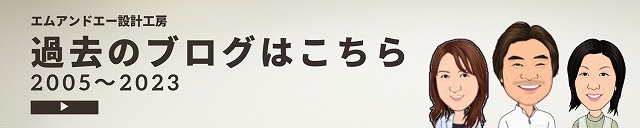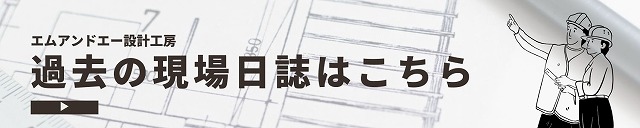\お気軽にお問い合わせください/
住宅今昔物語 昭和30年代から現代にかけて
今年は昭和100年という事で昭和を取り上げた番組をよく目にします。そんな中、少し前にNHKの番組で‘映像の世紀 バタフライエフェクト’での戦後から現代までを経済面から綴った番組を観ました。ちょうど私が生まれた昭和中期から平成にかけて住宅も、もの凄い変化がありました。というわけで今回は昭和30年代から現代までの住宅事情を私自身の生活を思い出しながら進めていきます。
昭和30年代(1955年頃)から令和7年(2025年)までの70年間は日本の住宅と住宅設備が劇的に変化した時代です。戦後の復興期から高度経済成長を経て人々の暮らしは便利で豊かになった一方で、失われた価値もあります。

・戦後から10年経った昭和30年代から昭和末期にかけて:憧れの団地、急増する核家族
戦後のバラックから10年が経ち、住宅は団地ブームとダイニングキッチンの普及がすすみます。住宅不足を解消するため、日本住宅公団が設立され、都市近郊に団地が建設されました。その団地の多くで採用されたのが、食事と就寝の空間を分ける「食寝分離」の考えに基づいた2DKプランです。暗く狭かった台所が、明るいダイニングキッチンとして独立したことで、食卓を囲んで家族が集まる新しいライフスタイルが生まれました。
また戸建て住宅では依然として木造平屋建てが主流でした。開放的な田の字型の間取り、縁側、土間など、日本の伝統的な様式が受け継がれていました。
住宅設備はというと暖房は火鉢や七輪、調理はかまどなど、薪や炭が主な燃料でした。風呂はまだ薪で沸かすのが一般的で、田舎では五右衛門風呂が当たり前でした。私も幼いころに行った母の田舎では、五右衛門風呂に入った経験があります。
また水道、ガス、電気といったインフラは徐々に整備されつつありましたが、十分に行き渡っているとは言えず、共同便所や共同浴場も珍しくありませんでした。洗濯機や冷蔵庫といった家電製品はまだ高価で、一部の富裕層しか持てない「三種の神器」でした。
さらにインフラの未整備や家電製品の普及率の低さから家事労働は重労働でした。また汲み取り式便所や共同の水回りなど、衛生面でも現代に比べるとかなり劣っていました。
ですが今との大きな違いは近隣との関係です。団地では隣近所との付き合いが密接で、子どもたちは路地や公園で遊ぶのが日常でした。地域全体で子育てをするような、温かいコミュニティが存在していました。まさに映画「オールウェイズ」そのものです。
住宅の設計では自然との共生を生かした設計で、縁側や風通しを考えた間取りは、日本の高温多湿な気候に適応した設計でした。夏は涼しく、冬は暖かいといった自然の恵みを活かした暮らしが営まれていました。しかし、仕切りが少ない間取りのため、家族のプライバシーは限られていました。個人の空間を持つという考え方はまだ一般的ではありませんでした。
この当時はまだ猛暑日などは無く、真夏でも30℃くらいとエアコンが無くても扇風機などで涼が取れたのです。この頃はまだ気候変動や地球温暖化などの言葉もない時代です。
昭和末期〜平成初期:マイホームと設備の近代化
住宅は戸建て住宅の量産化が始まり、土地神話と高度経済成長を背景に、庭付き一戸建てが憧れの対象となり住宅メーカーが台頭してきます。
暮らしではダイニングキッチンに加えてリビングが加わったLDKが主流になり、家族が集まる場がより広くなったの同時に核家族化がすすみました。
また大きな規模の地震を経て耐震基準が見直され、1981年の新耐震基準の導入など建物の安全性が向上しました。
住宅設備では洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、エアコンといった家電製品が一般家庭に普及し、家事の負担が軽減されました。
水回りは近代化され、風呂やトイレが各家庭に完備されるようになり、水洗便所など清潔で快適な暮らしが実現し、お風呂はタイル張りのものが一般的でした。
家電製品の普及により家事の負担が軽減され女性の家事労働が劇的に楽になりました。これにより、女性の社会進出を後押しする土壌が作られてきました。
また住まいの快適性が向上。エアコン普及や冬場はコタツで暖をとるようになります。
今ほどではないものの断熱材や気密性が向上し、冷暖房機器の普及によって、一年を通して快適に過ごせるようになります。
核家族化がさらにすすむ事で隣人との関係希薄化し、家族の個室化が進み、近所付き合いが減少し始めました。コミュニティの温かみが失われつつある時代でもありました。
さらに住宅メーカーによる量産化が進んだ結果、個性のない画一的な住宅が増えました。
平成中期〜令和にかけて:多様化と高性能化
震災を経て省エネルギーや更なる耐震化が叫ばれ、現在に向けて加速。
高気密高断熱住宅が進化し、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)が普及し始めました。家電製品も含めて省エネ性能が飛躍的に向上しました。
住宅の間取りは多様化されライフスタイルの変化に合わせて、リビングを広く取る、使い勝手を考えた回遊性を高めるなど、自由な間取りが増えました。
また環境に配慮した自然素材の活用や、長く住み続けられる住宅、サステナブル住宅への関心が高まりました。
住宅設備ではまだまだですが、スマートホームの普及が進みます。IoT(Internet of Things)技術により、照明や空調などをスマートフォンで操作できるスマートホームが少しずつ実現しています。
浴室乾燥機、食器洗い乾燥機、床暖房、太陽光発電、蓄電池など、住宅設備が多機能化し、便利さと快適性が向上しています。また高齢化社会に対応し、手すりの設置や段差をなくすなど、バリアフリー化が進んでいます。
高気密高断熱性能とAIによる自動制御によって、家中の温度差がなくなり、常に快適な環境が保たれるようになりました。また家事の自動化や遠隔操作によって、家事にかかる時間や手間が大幅に削減され余暇を楽しむ時間が増え、生活の質が向上しています。
建物は耐震性や防災性が向上し、災害に強い家づくりが追求されるようになりました。
ただ便利さと快適性を追求する一方で、多くの住宅設備が電力に依存するようになり、エネルギー消費量が増大していて、設備の多機能化により故障時の修理費が高額になったり、メンテナンスが複雑になったりしてコrストがふくらむ側面もあります。
スマートフォンでのSNSなどの普及・進化によるテクノロジーの進化は暮らしを便利にした反面、家族が各々の部屋にこもる時間が増え、コミュニケーションが希薄化する原因にもなり得ます。
戦後の昭和30年代から令和7年までの住宅の歴史は大きな地震や災害を経て、利便性、快適性、安全性の向上をひたすら追求してきた道のりでした。その一方で、失われていったものもあります。温かい近所付き合い、自然との共生、そして手作りの温かみです。令和の時代、私たちは便利さだけを求めるのではなく、昔ながらの知恵と最新の技術を融合させ、人と人、人と自然が調和するサステナブルな住まいを築くことが求められています。