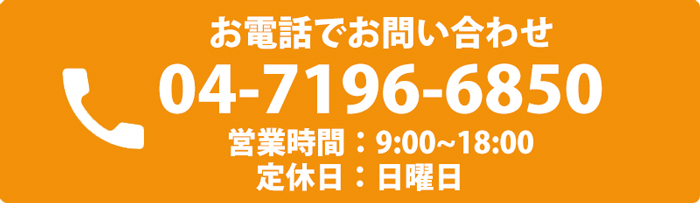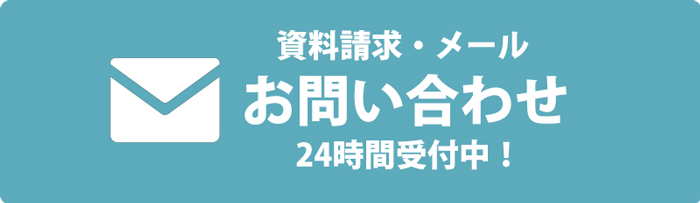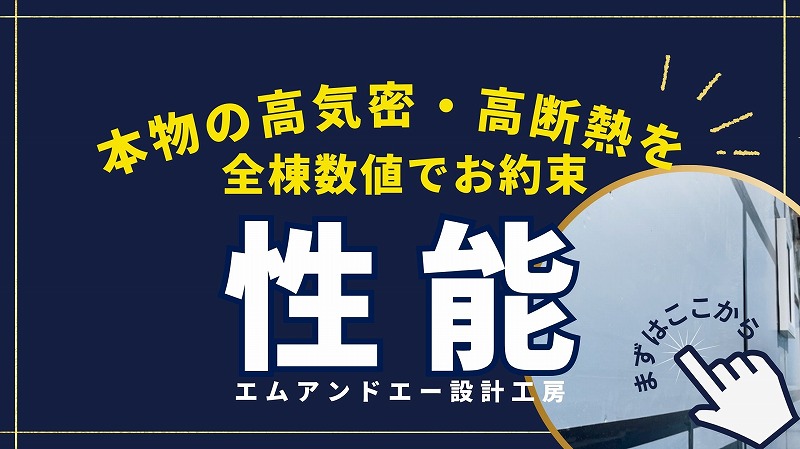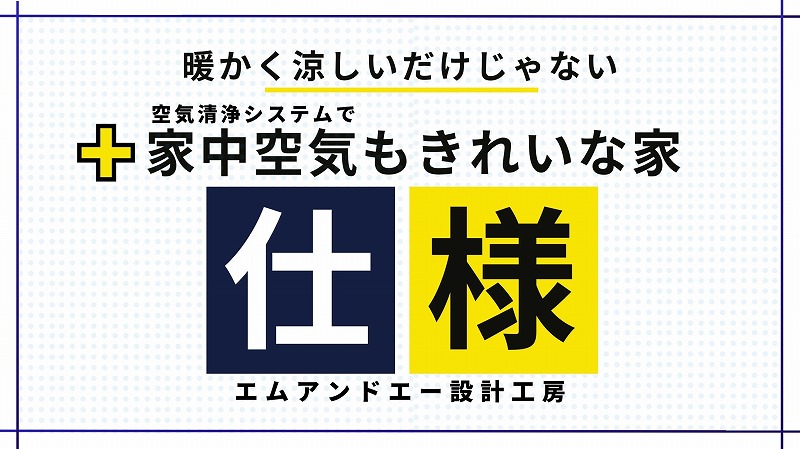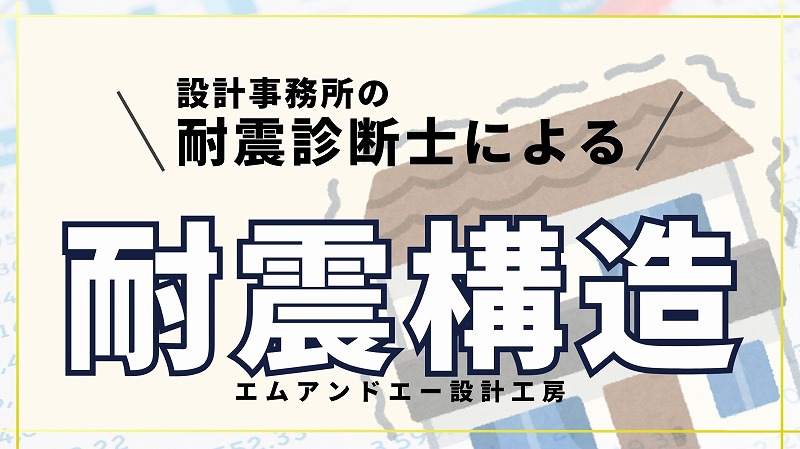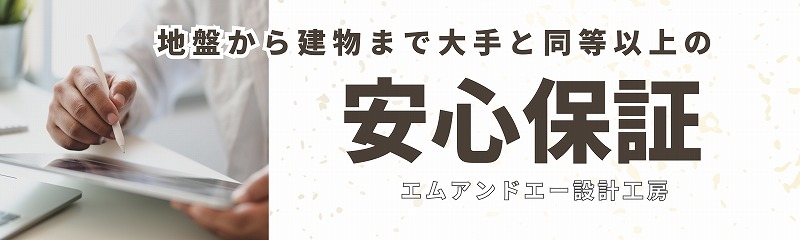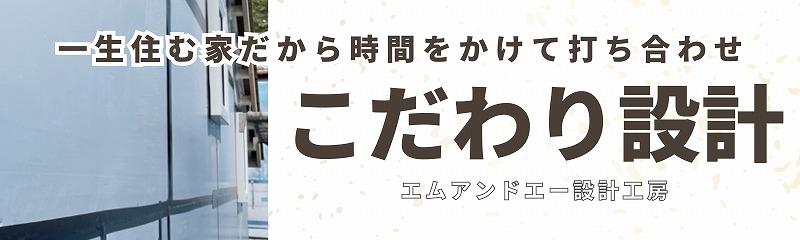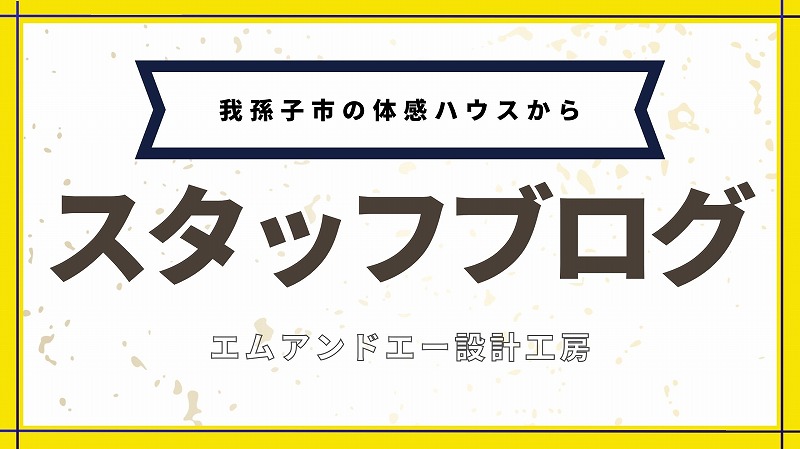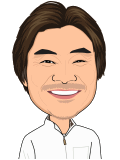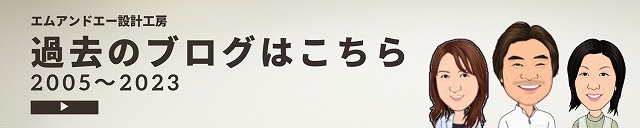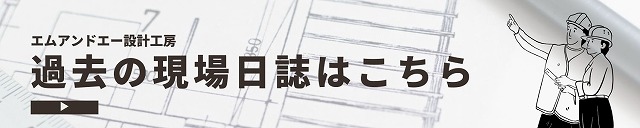\お気軽にお問い合わせください/
住宅業界転換期
2025年4月以降、日本の住宅業界は複数の法改正と社会経済の変化が重なり大きな転換期を迎えています。特に大きな影響を与えているのは、「建築物省エネ法改正による省エネ基準適合の義務化」と「建築基準法改正による木造住宅の審査強化(いわゆる4号特例の縮小)」です。これらに、資材価格の高騰、人手不足、そして金利上昇という経済的要因が加わり、住宅の建て方、価格、そして住まい手の意識までが大きく変化しつつあり住宅業界は転換期を迎えています。
そこで今回はこれらの問題を客観的に考えます。
法改正がもたらす住宅品質の向上とコスト増
(1) 省エネ基準適合の完全義務化:住宅性能の底上げ
2025年4月からは、原則としてすべての新築住宅に対し、省エネ基準への適合が義務付けられました。これまでは300平方メートル未満の小規模な住宅には適合義務がなかったため、多くの木造戸建住宅が対象外でしたが、今回の改正で対象が拡大されました。
この制度の義務化により、住宅の断熱性能(断熱等級4以上)や設備性能が底上げされました。これにより省エネ性が高くなり、冷暖房効率などの光熱費の削減や快適な室内環境の実現につながります。
一方で、建材などの資材や高性能な断熱材やサッシなどの採用が必須となるため、建築コストは上昇傾向にあります。また、設計・施工段階での審査手続きが増え、設計期間や工期が長期化する事態となっています。

(2) 4号特例の縮小:木造住宅の安全審査強化
これまで木造2階建て以下の小規模な住宅には、構造審査が簡略化される「4号特例」が適用されてきました。しかしこの間にはいくつもの問題が重なり、4号特例の見直し論が出て、今回の改正に繋がりました。そして本年4月からの改正建築基準法の施行により、この特例が事実上廃止され多くの木造住宅も構造安全性の審査が厳格化されました。
この改正で厳格な構造計算や確認申請手続きが求められることで、木造住宅の耐震性がさらに向上することが期待されてます。これは、近年の大地震の教訓から生まれた、災害に強い住まいづくりへの転換と言えます。
さらに従来よりも詳細な図面の作成や審査が必須となるため、設計・施工業者には大きな事務的・技術的負担がのしかかっています。これが建築コストや工期の増加につながる一因となっているのも事実です。

コスト増と金利上昇のダブルパンチ
(1) 止まらない資材価格の高騰と人件費の高騰
2020年代に入ってからの「ウッドショック」に代表される資材価格の高騰は、2025年になっても続いて現在では100万円/坪といわれています。さらに資材価格だけでなく、職人不足による人件費の上昇もコスト増に拍車をかけています。
資材価格の高騰では海外からの輸入木材に加え、現在では鉄鋼やセメントなども製造コスト増により価格が上昇しており建築費用全体を押し上げています。
また2024年4月に適用された建設業への時間外労働規制(いわゆる2024年問題)に加え、2025年の法改正による業務負担増もあいまって、人手不足はさらに深刻化しています。
(2) 金利上昇と住宅ローンの見直し
長期にわたった低金利時代が終わりを告げ、住宅ローン金利も上昇基調にあります。特に長期金利に連動する固定金利は上昇が顕著で、現在では変動金利も少しずつですが上昇傾向にあり住宅業界は厳しい状況にあります。
金利上昇は住宅購入者の返済負担を増やすため、購入意欲に影響を与えます。高所得層や資産を持つ層にとっては影響が限定的である一方、若年層や中間所得層にとっては、より慎重な資金計画が求められるようになります。
また住宅ローン戦略の変化としてこれまで主流だった変動金利一辺倒の考え方から、固定金利とのバランスを考えるなど、住宅ローン戦略を見直す動きが活発になっています。
このように住宅業界を取り巻く環境は大きく変化し縮小基調に入っているように感じます。