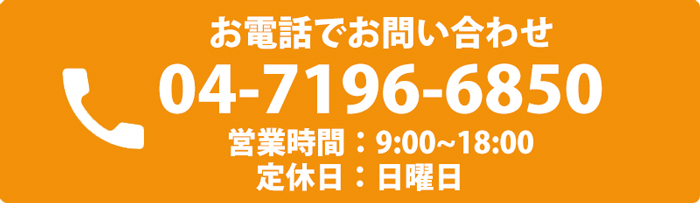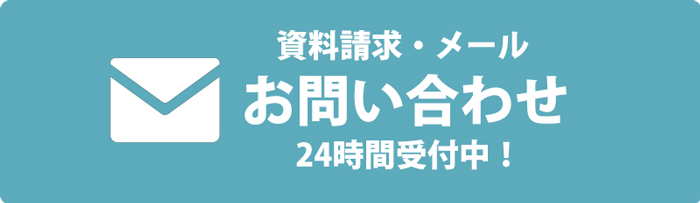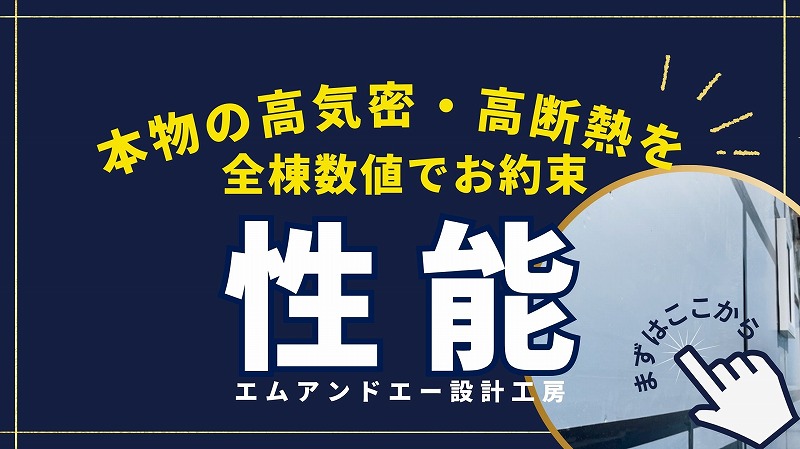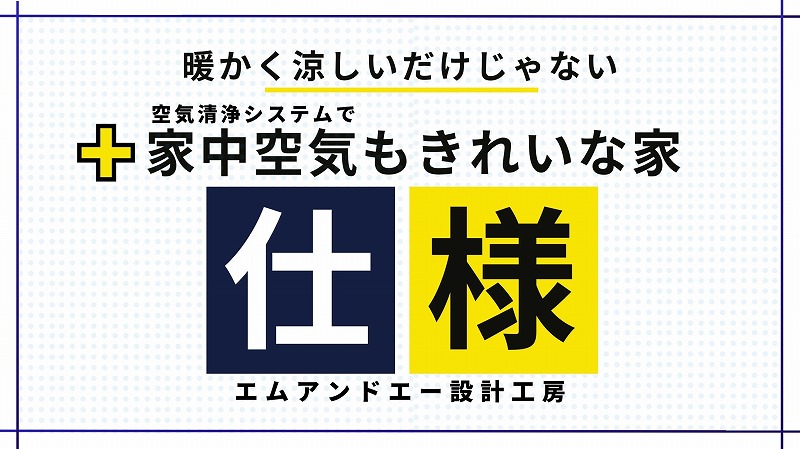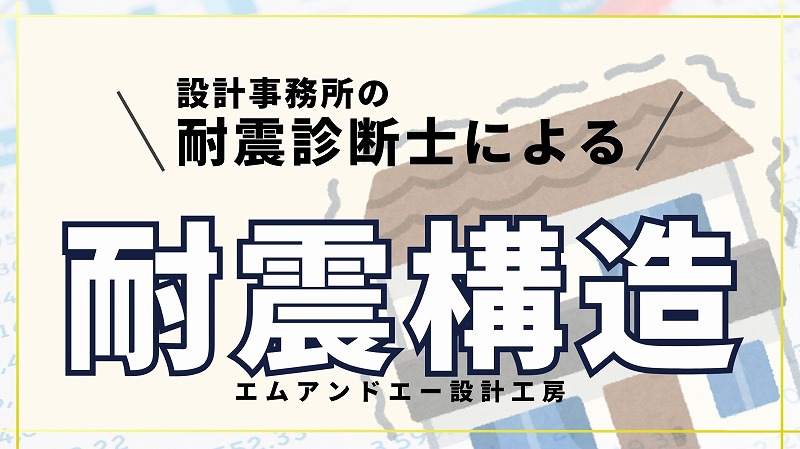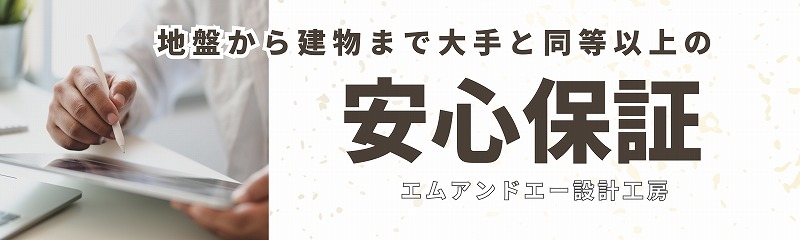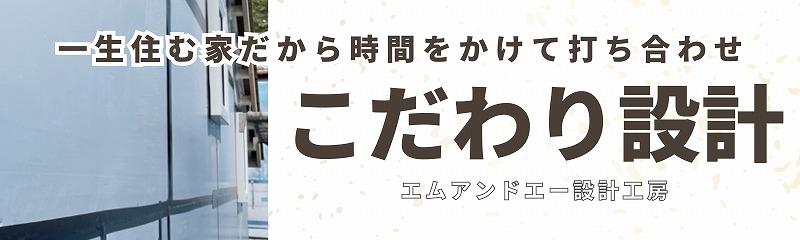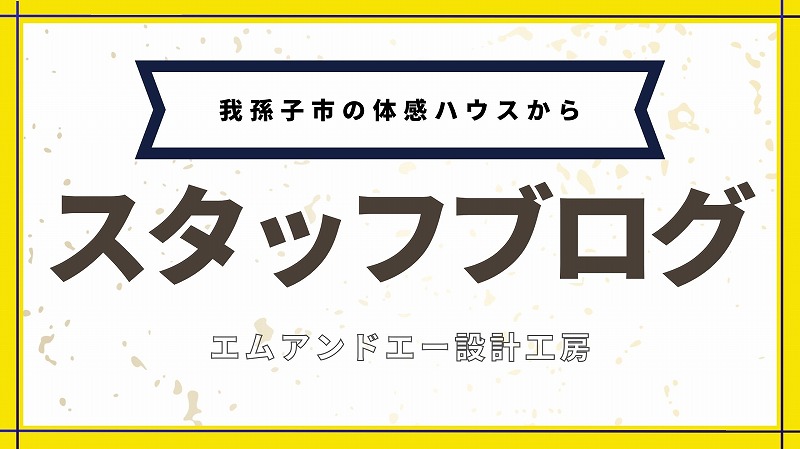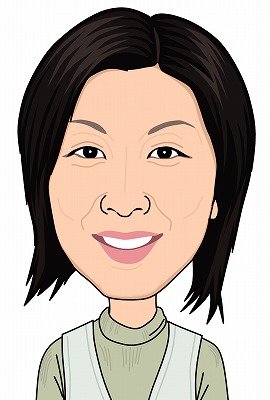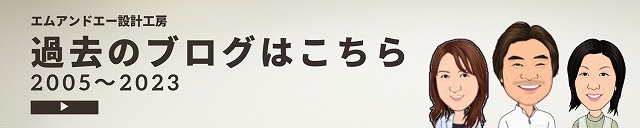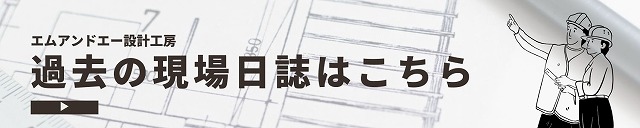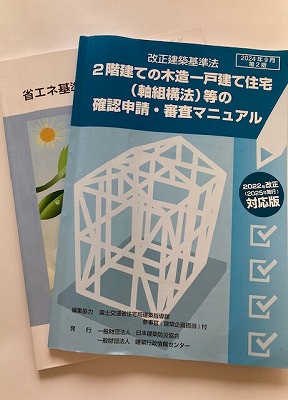\お気軽にお問い合わせください/
壁量計算について(by堀)
壁量計算とは、木造建築物の構造計算の一種です。
木造建築物が、外部からかかる「地震力」または「風圧力」に耐えられる壁を、必要な分だけ確保できているかを、壁量計算で検討します。
以前は、条件を満たす小規模な木造住宅などは、省エネ・設備・防火避難関係の規定とともに構造の一部の規定も審査・検査が省略され(4号特例)、構造計算もその省略される一つでした。
2025年4月1日から改正省エネ法・建築基準法等が施行され、
例えば 2階建て以下かつ延べ面積300㎡以下という一般的な木造戸建て住宅は、4号特例の見直しにより、構造関係規定も審査対象となりました。
構造計算の種類も様々ですが、壁量計算は特別なプログラムを使用する必要もなく、簡易にできる計算となります(その分、使用できる対象も小規模な木造建築物に限られます)。
壁量計算では、まず計画建物に、基準としてどれだけの壁量(耐力壁の長さ)が必要か、を算出します。
その「必要壁量」と、実際の計画で設置される「設計壁量」を比較し、設計壁量が必要壁量を上回れば適合、となります。
<必要壁量>
必要壁量は、「地震力に対するもの」と「風圧力に対するもの」の2通りを算出します。
-1.地震力に対する必要壁量の算出
地震力に対する耐力壁を算出するには、基本的に「階ごとの床面積(㎡)」×「床面積当たりの必要壁量(cm/㎡)」の計算を行います。
この「床面積当たりの必要壁量(cm/㎡)」は、改正前の基準法では階および、屋根の材料が重いか軽いか によって決まった数値を用いていましたが、改正後はまずこの数値を算出するのに、様々な係数や その階に係る荷重といった別の数値を用いる、複雑な計算が必要になりました。
そのため、より簡単に必要壁量(正確には床面積に掛ける数値)を算出できるよう、
表計算ツールや早見表が公開されました。
表計算ツールおよび早見表は、「公益財団法人 日本住宅・木材技術センター」や、
「一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会」(枠組壁工法の場合)のホームページから取得できます。
表計算ツールの方では、
各階の階高・面積、屋根・外壁の材料、断熱材・太陽光発電設備等の荷重などの数値を表内に記入すると、「階の床面積に乗ずる数値」が自動的に算出されます。
早見表を使用する場合は、
太陽光発電設備の有無、各階の階高、2階/1階の面積の割合 によって種類分けされた表が多数ありますので、
該当するものを選択し、その表の中で「屋根・外壁の仕様」から該当する「階の床面積に乗ずる数値」を探す、ということになります。
→「階ごとの床面積(㎡)」×「床面積当たりの必要壁量(cm/㎡)」・・・「地震力に対する必要壁量(cm)」
-2.風圧力に対する必要壁量の算出
風圧力に対する必要壁量の算出には、建物の床面積ではなく見付け面積・・・
「風の力を受ける面」の面積を用いて、各階・各方向(X・Y方向)ごとに、必要壁量を算出します。
風圧力に対する必要壁量については、法律の改正は無く従来通りです。
各階の床面から1.35m以下の部分を除いた面積を、見付け面積として算出します。壁の厚さ・屋根の厚さも考慮します。

→「各階・各方向の見付け面積(㎡)」×50(特定行政庁が地域によって50~75の間で定めている場合あり)
・・・「風圧力に対する必要壁量(cm)」
以上で、必要壁量の値が出そろいました。
各階・各方向において、
地震力に対する必要壁量と風圧力に対する必要壁量を比較し、大きい方を必要壁量とします。
2階建てであれば、
1階 X方向・1階 Y方向・2階 X方向・2階 Y方向 の4つの必要壁量と設計壁量を算出する必要があります。
よって設計壁量も、各階、またX方向・Y方向に分けて算出し、それぞれ必要壁量と比較する必要があります。

また「設計壁量(cm)」は、計画建物に存在する耐力壁の長さをそのまま算入、とは限りません。
工法の別、壁の面材の種類、釘打ちの方法などによって、「壁倍率」という数値が決められており、強い壁ほど倍率が高くなっています。同じ長さの壁でも、倍率が高ければより設計壁量の数値を満たせる、ということになります。
各階・各方向ごとに壁の長さに「壁倍率」を掛け、その合計で得られた数値が設計壁量となります。
例えば、石膏ボード 厚さ12.5㎜を片面に貼っている場合は1倍(枠組壁工法の場合)。
同じ壁に複数の仕様が併用されている場合、その壁倍率を合算できるので、石膏ボード 厚さ12.5㎜を両面に張れば壁倍率は2倍となります。
耐力壁の種類と壁倍率は告示とよばれる情報で公開されており、その条件に合った面材や筋交いの種類、規格、面材の厚さ、釘の種類、釘の間隔などを守る必要があります。そのほか、大臣認定を取得した耐力壁もあり
法改正前は、壁倍率は5.0が上限とされていましたが、改正後は上限が7.0まで引き上げられました。
建物の床面積・見付け面積から必要壁量を、各壁の仕様やその長さから設計壁量を算出。各階、各方向において設計壁量が必要壁量の値を上回っていれば、壁量が確保できているとみなされます。
ですが、地震に強い家とするには、単に耐力壁を必要分以上確保するだけでなく、建物全体にバランスよく配置することも重要です。