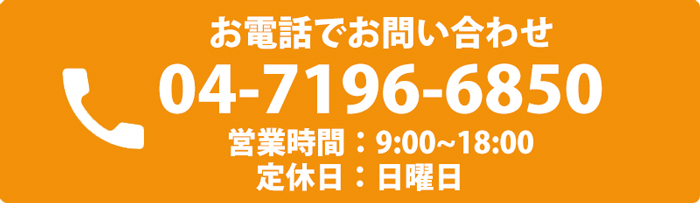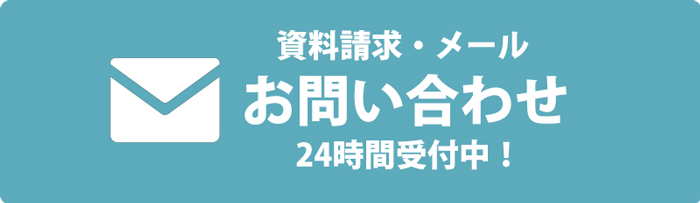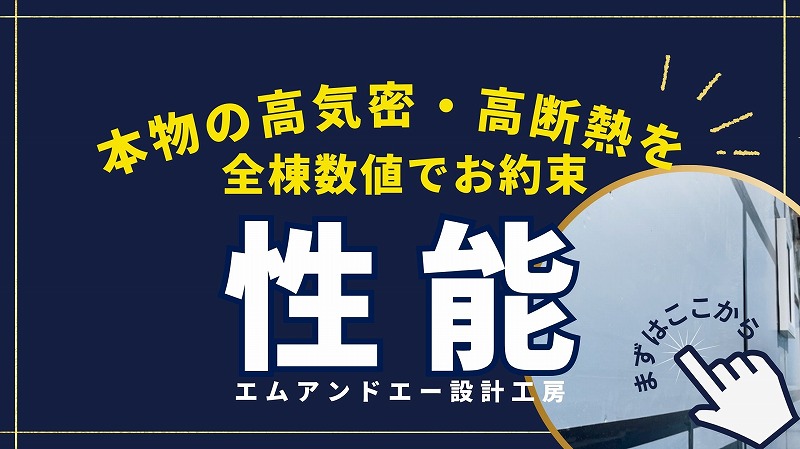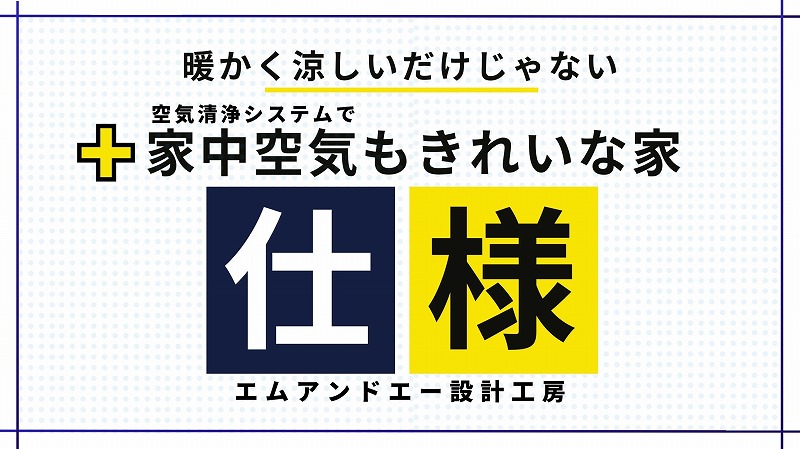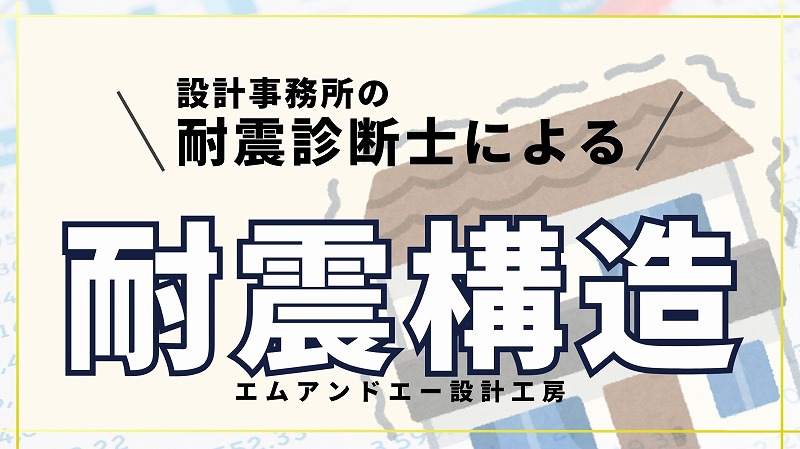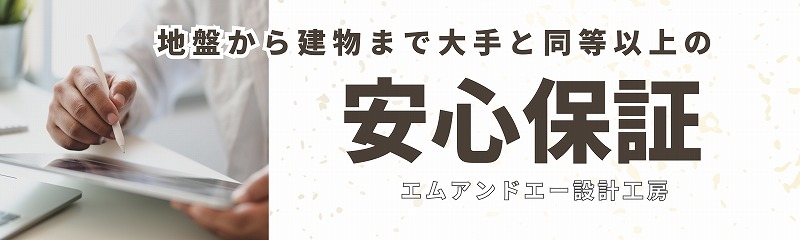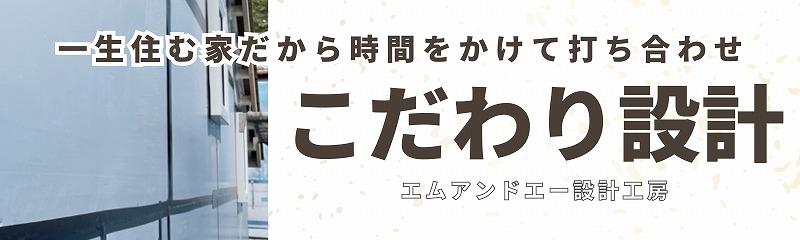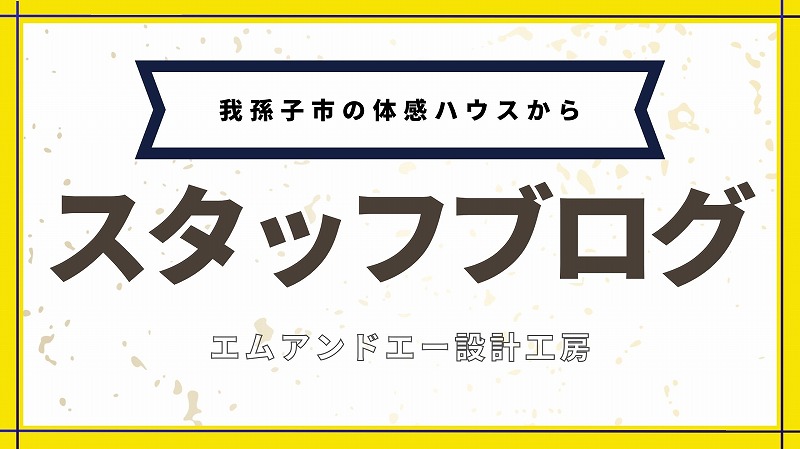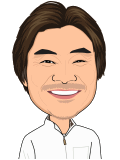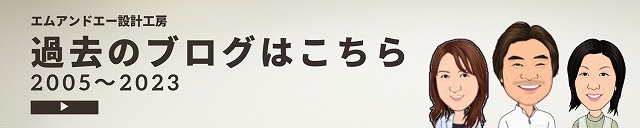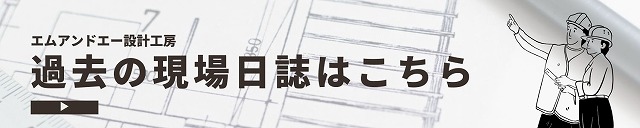\お気軽にお問い合わせください/
日本における洋館
日本における洋館の歴史は、明治時代にさかのぼります。明治維新後、日本は急速な近代化と国際化を遂げる中で、西洋からの文化や技術を積極的に取り入れるようになりました。そう文明開化です。特に外交や貿易の中心地であった横浜や神戸などの港町では、外国人居留地が設けられ、そこに洋風の建物が建てられるようになりました。横浜では現在の山手、神戸では北野異人館街などがそれにあたります。当時のまま、というわけではなく移築などではありますが、当時の趣を残してたたずんでいます。これらの建物は、当時の外国人居留民の生活や文化を反映するものであり、当時の日本人にとってはとても不思議であり、かつ新鮮な風景だった事でしょう。

洋館の建築様式は、当時の建築様式を模範として当初は外国人建築家によって設計されることが多かったのですが、やがて明治時代中期から大正時代になると日本人建築家もその技術を習得し、独自のスタイルを築いていきました。明治中期以降になると日本政府の重要な公共建築物や、富裕層の邸宅などでも洋風建築が採用されるようになり、洋館の普及が進んでいきました。
その時代での有名な建築に今では現存しない鹿鳴館や三重県桑名市にある六華宛(旧諸戸家)、上野にある旧岩崎邸などがあります。そのどれもがイギリス人建築家のジョサイア・コンドル氏が設計しています。

洋館の特徴には、いくつかのポイントがあります。第一に、洋館はヨーロッパの建築様式を基にしています。そのため、煉瓦や石材などを用いた外壁や、アーチ型の窓、装飾的な柱などが特徴的です。屋根の形状も、日本の伝統的な建築とは異なり、平屋根や勾配の緩やかな屋根やドーマー窓などが多く見られます。その外観を眺めているだけで何故か優雅な気持ちになれるのも洋館の魅力です。
また多くの洋館には和館が併設されている事が多くあります。当時では洋館は応接としての役割、実際の生活は日本間のある和館で営んでいた事がわかっています。


洋館の内部にも大きな特徴があります。高い天井や大きな窓、広い廊下、洋風の内装や家具などが取り入れられ、また冬の寒さを考えての暖房設備など当時の快適な居住空間として設計されています。特に大正から昭和初期にかけての洋館は、その豪華さや洗練されたデザインで、当時の文化的・社会的な象徴としての役割を果たしています。
当時の洋館は政界や財界の大物が好んで建築しているので、会社や個人の顔としての役割もあったのです。


洋館はまた、日本の都市部における景観形成にも重要な役割を果たしました。特に東京や横浜などの大都市では、外国人居留地や外交使節団の建物が集まり、洋館が密集する地区が形成されました。これらの洋館は、その多くが関東大震災によってその多くが失われましたが、その後の都市計画や景観保存活動においても重要な文化財として保護され、多くが現在でも保存されています。
洋館の建築は、単なる建物以上の意味を持っていると思います。それは、日本の近代化と国際化の歴史を物語る重要な遺産であり、その建築様式やデザインは時代の流れや文化の交流を反映しています。現在でも、洋館は多くの人々にとって魅力的な建築物であり、歴史的・文化的な財産として大切にされています。
横浜山手や神戸北野などをはじめとして日本国内には未だに多くの洋館が存在し、その土地の歴史と共に人々と根付いています。


私自身も多くの洋館見学をしながら、そのデザインや間取り、考え方を今の住宅に生かせないかと常に考えています。
古い洋館の維持保全は大変だと思いますが、この優雅な洋館が次の世代にも引き継がれることを願っています。